漢検を勉強するとき、部首パートの優先度自体はあまり高くありません。
ここに時間をとってしまうのはよくないからです。
理由は2つ。
①10点でしかも1点ずつということ
②覚える範囲も多く、ひっかけも多い
しかし、特に2級以上になると、この10点を落としてしまうと、他のパートで補わなければなりません。
できれば、5点から6点はとっておきたい。
でも勉強法がこれまた難しい。
漢字の部首はとにかく覚えるっていう結論になりそうですが、それでは意味がないです。
それを攻略していくのがこの記事。
数点の差で合否が分かれるのが漢検です。部首での数点分の獲得が合格になるかもしれません。
※当記事のリンクは、アフィリエイト広告を利用しています。
部首の範囲ってどうなの?
(今回使用したテキストはこちら)
こちらが最新版。
出題範囲については、準2級配当漢字が中心と言われています。
この記事は、漢検2級を対象として書いていますが、準2級にも応用が可能です。
準2級配当漢字については、テキストの222Pに載っています。
余裕のある方はチェックしてみてください。
また、部首については、この参考書で数えてみたら全部で277個ありました。
非常に多いですね・・・。
部首の覚え方・見分け方
まず前提として、100個以上ある部首を全て覚えるのは、配点が1点ということからも、効率的ではありません。
テキストの問題に絞って覚えていきましょう。
絞っても、約200個の漢字がありますから、正直これだけ覚えるだけでも非常に大変です。
「あくまで余裕があったら」載っている問題以外の漢字も覚えていきましょう。
部首の「名前」は正解には不必要
漢検2級の問題は「漢字の部首を記せ」です。
「部首の名前」は聞かれていません。
答え方は、部首の名前ではなく、部首自体を書きます。
これはクイズ番組の対策ではありません。漢検対策です。
なので、部首の名前は合格には不必要。
大事なのは、正しい部首が選べるかどうか。
「利」の部首は「リ」でOK。
りっとうなんて頭に入れる必要はありません。
※「あくまで漢検に合格するということにおいては」です。
次は見分け方の1つとして、たくさんある漢字を2つに分けていく作業を行います。
部首を見分けるには大事な作業です。
見分け方ポイント①(漢字の分別その1)
問題集に載っている漢字を2つに分けていきます。
まずは
「この部首以外考えようがない断定できる漢字」です。
例えば「彰」という漢字について「章」へんというものは存在しません。
従って、ノが3つの部分(さんづくり)が答えになります。
見分け方ポイント②(漢字の分別その2)
もう1つは
候補が2つ以上ある部首です。
例えば「塁」という漢字について、「田」の可能性もあれば「土」の可能性もあります。
そのような漢字は要チェックです。
これが結構難しい。
見分け方ポイント③断定できる部首を攻略
極論、277個の部首を全て覚えていたら、その1に分類される漢字は即答できます。
ただ、この状態にするのは非常に難しいです。
問題集の漢字から、部首を1つずつ覚えていくというのが一番いいかと思います。
単語帳の表に漢字、裏に答えを手書きで書くのが一番いいですが
面倒という方は、こんな感じで一問一答形式でエクセルを載せるのもいいと思います。
左右の④をみてみると、部首はもちろん、章へんがないということも同時に覚えることができます。

これは私のやり方ですが、パソコンだと手書きができないので、こんな感じで覚えるのもおすすめ。
とにかく、正しい部首さえ選べれば1点です。
また、漢字がそのまま部首になるという一種のチャンス問題もあります。
こんな漢字がでたら得点源です。
缶 甘 辛 馬 鬼
革 玄 斗 鼓 舟 骨
などなど。
漢字そのものが答えなので、上記の漢字は覚えておきましょう。
(ちょっとした攻略法)
分かりにくい部首の例として
「横棒(一) 縦棒(|) 点(、) くち(口)」
の4つが主にあります。
その中でも口(くち)は答えになりやすいです。
困ったら「口」にしとけ!と覚えておくといいかも。
部首を実際に勉強していくと、この意味が分かるかと思います。
※あくまで最後の手段です。普通に外すこともあります。
さて、もう1つの断定できない漢字についてですが
どんな漢字が候補が2つ以上あるのか分からないと思いますので、間違えやすい漢字の部首を20個厳選しました。
覚え方の解説もしています。
間違えやすい・判断しにくい部首20選
1 朱:木(きへん)
→ぱっと見て、どこが部首なのか見つけにくいです。よくよくみると「木」が隠れていますね。
2 弔:弓(ゆみ)
→たてぼう(|)と悩みますが、弓です。
3 甚:甘(あまい)
→こちらも部首がみつけにくいです。「甘」が隠れていると言われても、えっ?って思いませんか。
ということは・・・出やすいということですね。
4 戻:戸(とだれ)
→大の方を選択しやすいかと思います。成り立ちをみてみると、戸は入口、大は犬からきてるようです。なので、戸が正解。
5 窯:穴(あなかんむり)
→よくある、点4つの方の部首ではありません。ピザ窯は穴が空いているので、穴と覚えておきましょう。
6 臭:自(みずから)
→こちらも大ではありません。
7 呉:口(くち)
→こまったときの「口」。
8 凹:(うけばこ)
9 凸:(うけばこ)
→凶のメの外の部分です。どちらも同じ部首なんて面白いですよね。というか、同じなので覚えやすい。
ちなみに「出」も同じ部首です。これは知ってないと絶対答えられないですね。
※豆知識:凸凹だと(でこぼこ)凹凸だと(おうとつ)です。
10 致:至(いたる)
→致(す)、至(る)なので、そのまま選べばいいだけなのですが、のぶん(右の部分)が結構有名な部首なので、そちらを選ばないように気を付けましょう。
改や数など、たくさんありますからね。
11 美:羊(ひつじ)
→「甚」レベルに見つけにくいです。書き順を思い返してみると、確かに羊と書いてるわ。となります。
12 耗:すきへん・らいすき(左の部分)
→「耕」と「耗」ぐらいしかこの部首はありませんので要チェック。
13 塑:土(つち)
→月と迷いますね。塑の意味は「粘土をこねて形を作る」という意味。ということは「土」と覚えておけばOK。
14 塁:土(つち)
→「田」がありますが、野球から土が連想されるので「土」。
15 累:糸(いと)
→こちらも「田」と迷いますね。こちらは連想して覚えようがないので、糸と覚えるしか基本ないです。
※では「田」はあるのか?と思うと思いますが「男」「町」「界」などたくさんあります。
16 夫:大(だい)
→散々ひっかけがありましたが、夫は「大」。
17 尿:(かばね)戸の上の横棒がない部首
→尿から水分を連想されやすく、水と書きがちですが、これがひっかけ。要注意です。
18 軟:車(くるまへん)
→車と軟に何の関係が・・・と思いたくなりますよね。
欠(あくび)を選ばないように。
19 某:木(き)
→結構「甘」と書きがちです。
20 興:臼(うす)
→臼が隠れています。臼の部首は、臼自体と興しかないので、細かいこと考えずに覚えてしまいましょう。
あくまでも、部首パートにはあまり力は入れずに、勉強配分を考えることが大事です。
漢検2級全体の攻略記事です。

漢検の四字熟語に関する特化記事です。
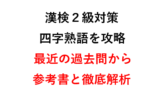
漢検準2級の攻略記事です。




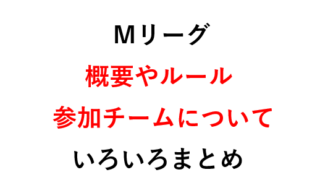



コメント