漢検2級の合格率ですが、結構難しく、約30%前後です。
一方準2級だと、約40%近くにまで上がります。
私はどちらも取得していますが、実際、そこまで難しさは変わらないなという印象でした。
でもこうして10%ぐらいの合格差がある。それは一体なんなのでしょうか。
それは合格基準です。
約70%:(140/200)→準2級
約80%:(160/200)→2級
となっており、この20点が結構重くのしかかります。
この20点を補えずに、特に160点に数点届かずで落ちてる人、結構いるんです。
「漢検2級なんて、まあそれなりに数週間勉強すればとれるでしょ」
この考えで挑むと玉砕します。
ちなみに私、1回目は落ちました。数点届かずのパターン。勉強期間は約1ヶ月だったかな。
準2級の取得時に、同じような感じでいけると思っていたのが落とし穴でした。
この数点は簡単に埋められるような差ではありません。
「たった数点ではなく、数点も足りてない」
落ちるべくして落ちました。
本記事では、その数点を埋めるべく「とるべき数点分をしっかりとる」を意識した、各パート毎の攻略法も書いています。
お伝えするのは、大きく分けて以下3点。
①おすすめのテキスト・問題集の紹介
②パート別の勉強法
③覚えておきたい、間違えそうな問題集
受験料も4,500円と高く、チャンスは年に基本3回。
私と同じように再受験というのはこの記事を読んだ方には受けてほしくありません。
まずは、漢検2級に合格するための勉強法として、必要な5つのポイントをお伝えします。
勉強する上で、非常に大事です。
合格するためには、この5つのポイントを意識してください。
①参考書は1冊に絞る
②勉強期間は最低でも1ヶ月(2ヶ月くらいが理想)
③勉強するときは必ず暗記シートを使用
④パート毎に目標点数を決める
⑤書き練習は、頭に漢字が浮かぶようになってから
(詳細は、同音・同訓漢字のページ)
合格すれば、このような賞状がもらえます。
就職試験の武器や、大学によっては単位補助にもなります。
持ってて損はありません。

※当記事のリンクは、アフィリエイト広告を利用しています。
おすすめのテキスト・問題集について
私が合格したときに使った本がこちらのシリーズです。
「頻出度順漢字検定2級 合格!問題集」
資格試験には必須だと思っている暗記シートもついており、一番勉強しやすいです。
こちらが最新版。
このシリーズの1冊だけを徹底的に抑えました。
漢検2級合格のための勉強法
テキスト・問題集は1冊のみ
ポイント①の部分です。
※漢検2級の満点を目指すのではなく、あくまで合格がゴール
→漢検2級マスターを目指したいなら、別な参考書をもう1冊買いましょう。
1冊を完璧に近い状態にすれば、ほぼほぼ受かります。
そのためには、数週間では天才でない限り正直厳しいです。
勉強期間は、最低でも1ヶ月、2ヶ月ぐらいは欲しい(ポイント②)
1ヶ月で1つの問題集をマスターできるほど、漢検2級は甘くはありません。
これは他の資格試験にも言えると思います。
暗記シートが必須
ポイント③の部分です。
暗記をするには、思い出す練習を何度もすることが大事です。
何回書こうが覚えられないものは覚えられません。
書いて覚えようとすると疲れますし、時間もかかります。いいことなし。
また暗記シートを使わないと、覚えた気になってしまい、本番で全部頭から抜けてしまうことがあります。
漢検2級合格のためのパート別対策
それぞれのパートに分けて、対策法、間違えそうな問題をまとめました。
それぞれの目標点数も書いておきました。
これは、それぞれ目標点数を設定することで、160点以上をどうとるかのイメージをつけるため。
あくまで例なので、自分にあった点数配分を考えてみてくださいね。(ポイント④)
こちらで用意した対策問題を確実に覚えて、残りの部分は参考書で勉強していきましょう。
対策問題は、紹介した「頻出度順漢字検定2級 合格!問題集(2023版)」を参考にしています。
見比べながら対策してみてください。
読み(1点×30)
目標(28/30)
この30点は取り逃せないです。
悪くても落とせるのは2問まで。
漢検2級の漢字が読めればいいと思いきや、意外なところに落とし穴があります。
()が漢字の読み方の注意点です。全部で50個用意しました。
暗記法の1つとしてこんな記事も書いてます。
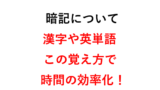
対策問題
1 妖艶:ようえん(艶)
2 象牙:ぞうげ(牙)
3 歯牙:しが(牙)
4 玩具:がんぐ(玩)
5 橋桁:はしげた(橋)
6 領袖:りょうしゅう(袖)
7 羞悪:しゅうお(悪)
8 貼付:ちょうふ
9 藤色:ふじいろ
10 爪弾く:つまびく
11 菜箸:さいばし(箸)
12 汎愛:はんあい(汎)
13 凡庸=ぼんよう(凡)
14 煮沸:しゃふつ(煮)
15 愁嘆場:しゅうたんば(場)
16 軍靴:ぐんか(靴)
17 嫡=ちゃく 衷=ちゅう 弔=ちょう
18 荘厳=そうごん(厳)
19 建坪=たてつぼ
20 釣果=(釣)
21 紛糾=ふんきゅう(糾)
22 女傑=じょけつ(女)
23 衣鉢=いはつ(鉢)
24 洪積世=こうせきせい(世)
25 減俸=げんぽう(俸)
26 押韻=おういん(押)
27 凸凹=でこぼこ 凹凸=おうとつ
28 耗弱=こうじゃく(耗)
29 聴聞=ちょうもん(聞)
30 納屋=なや(納)
31 納戸=なんど(納)
32 格子戸=こうしど(格)
33 秘奥=ひおう(奥)
34 市井=しせい
35 功徳=くどく
36 好事家=こうずか(ず)
37 年端=としは
38 普請=ふしん(請)
39 庫裏=くり
40 反物=たんもの
41 暮色=ぼしょく(色)
42 山車=だし
43 帰依=きえ(依)
44 勤行=ごんぎょう
45 築山=つきやま
46 建立=こんりゅう
47 衆生=しゅじょう
48 緑青=ろくしょう 紺青=こんじょう
49 謀反=むほん
50 火影=ほかげ(火)
別記事で作成した読み間違えやすい漢字も、時間がある人は見ておいて損はありません。
下記リンクをクリックで読めます。
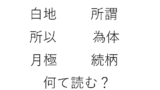
部首(1点×10)熟語構成(2点×10)
目標:(26/30)
この2つに関しては、対策本に載っている問題を何度も暗記シートを使って復習してください。
部首については、範囲も広く、ひっかけな部首も多いです。
1点ということもあり、優先度的には最後の方をおすすめ。
※部首の10点を捨てるというのは、合格するためには無謀な策です。
5,6点は最低でもとっておきたいところ。
以下の記事で詳しく攻略法を解説しています。

熟語構成については、2点と配点が大きく、記号問題でもあります。
この問題集では、熟語が全部で278個。
最低でも、参考書のCランク68個を抜いた残り210個は、確実に覚えましょう。
この20点分の5択を正解することは、合格に向けてかなり大事になってきます。
この問題は5つに分かれていて
A:同じような意味を重ねたもの(挨拶)
B:反対の意味(虚実)
C:上の字が下の字を装飾(僅差)
D:下の字が上の字の目的語、補語(懸命)
E:上の字が下の字の意味を打ち消しているもの(不屈)
以上5つです。
勉強法については、A~Eの漢字を分けて覚えるのが効果的。
①A、B、Eの3つの熟語を問題集から抜粋して覚える
②残ったCとDの熟語を抜粋して覚える
(CとDは消去法を利用するのも勉強の一つ)
1)A,B,Eの3つは、勘でも当たりやすいですし、割と覚えやすいです。
Aの場合、憧憬・賄賂など、同じ部首が並ぶときはほぼほぼ「ア」です。
※「贈賄」などの例外もあるので注意。
Bの場合、硬軟・点滅など、反対の意味なので、さほど難しくはありません。
Eの場合、主に「不」「未」が頭につく感じを選ぶだけです。
2)一番難しいのがCとDの選択になります。
CかD、覚えやすい方を勉強して、片方は消去法で答えられるようにするのも1つの方法。
もちろん、参考書の全部の熟語を覚えることが一番です。
四字熟語(2点×10、2点×5)
目標:(26/30)
四字熟語に関しては、2つに分かれており、計30点とこちらも大きいです。
次のパートの「対義語、類義語」がかなりの難関。
そこで少々コケてもいいように、四字熟語は確実に得点していきましょう。
問題の形式:10個の四字熟語。
前半:四字熟語の書き取り(20点)
後半:その漢字の意味を選ぶ(10点)
となります。
「載っている四字熟語はとにかく反復して覚える」に限りますが、書きで間違えそうな漢字を抜粋しました。
対策問題
1 盛者必衰(じょうしゃひっすい)の「衰」
2 怒髪衝天(どはつしょうてん)の「髪」
3 意気衝天(いきしょうてん)の「衝」
4 初志貫徹(しょしかんてつ)の「徹」
5 沈思黙考(ちんしもっこう)の「沈」
四字熟語について苦手な方が多いと聞いたので、四字熟語パートに特化した攻略記事を書きました。
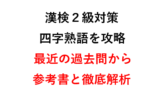
対義語・類義語(2点×10)
目標:(12/20)
かなり厄介なパートになります。
例えば、付与という漢字があるとします。
対義語の場合
①付与の意味が分かっていること
②反対の意味が分かっていること
③剥奪の漢字が書けること
ヒントは、ひらがなで書かれている言葉のみです。
この3つを満たして初めて2点獲得です。類義語も同じです。
かなり難しいですし、正答率も高くありません。
ここはなんとか6割ぐらいは最低でも取れるようにしましょう。
同音・同訓漢字(2点×10)
目標:(18/20)
書き問題ですが、同音・同訓は「難しい代わりに範囲が限定できる」のが利点です。つまり得点源です。
1つ1つをセットで覚えていくので尚更です。
問題集を暗記シートを使って、何度も何度も頭で繰り返し、
頭で漢字が浮かぶようになってから書き練習に入ってください。(ポイント⑤)
※これは全ての書き問題に共通します。
10回同じ漢字を書いている時間があったら、頭にその漢字が浮かぶように、何度もアウトプットしましょう。
例)
1 使者が女王にエッケンした。
2 課長のエッケン行為に困惑する。
という問題の場合
それぞれの熟語を頭の中で「謁見&越権」だなと思い浮かべれるように何度も繰り返すのが重要です。
これができてから、書き間違えがないように、謁とかの漢字を練習しましょう。
ここ、かなり効率面で大事です。
誤字訂正(2点×5)
目標:(6/10)
誤字訂正は、意外に平均点も低いです。
当然書き間違いやすい漢字が出題されます。
きちんと覚えているつもりでも、問題文のどこが間違いかすら気づかない。なんてこともあります。
貢献の字が更献と書かれていても、案外気づかないものです。
何より、誤字をあえて読ませることによって、本来の漢字を思い出しにくくするという効果もあります。
私もこれには結構悩まされました。
こうけんするを漢字にする→貢献と書ける
更献するを正しく直す→思い出せない
こんな感じです。
(勉強法)
誤字部分を見つけたら、その漢字を一端忘れるために、ひらがなにした状態で、漢字を思い出すことを繰り返す。
→更献と書かれていたら「こうけんする」と紙に書いて、そこから漢字を思い出す
という手順です。
実際にこれで、誤字訂正の正解率をアップさせました。
対策問題はこちら。
対策問題
1 飢餓(×危餓)
2 哀愁(×愛愁)
3 請負った(×受負った)
4 喚起させる(×換起)
5 先駆け(×先懸け)
送りがな(2点×5)
目標:(8/10)
送りがなは、漢字自体あまり難しくないのが多いので得点源です。
確実に点数を取っていきましょう。
対策問題はこちら。
対策問題
1 惜しいの「惜」
2 懐かしいの「懐」&送りがな
3 甚だしいの「甚」&送りがな
4 褒めるの「褒」
5 懲りるの「懲」
6 柔らかいと軟らかいの使い分け
7 薫るの「薫」
8 虐げるの「虐」と送りがな
9 慕うの「慕」
10 唆すの「送りがな」
書き取り(2点×25)
目標:(42/50)
これで合計166点で、合格基準に達します。
書き取りは50点分と、ここで躓いてしまうと、合格はほぼ不可能。
判定基準も、きちんとはねるところは、はねる、つきだすか、つきださないかなど、結構厳しいです。
1文字1文字しっかりとお手本の文字を見て練習をしましょう。
それでも優先度は、漢字が頭に浮かぶようにすることです。それから実際に書く練習をしても全く遅くありません。
書きで間違えそうな漢字を抜粋しました。
対策問題
1 軽蔑の「蔑」
2 渋柿の「柿」(なべぶたを書いて巾)
予備知識:こけらと書かないように。
3 半袖の「袖」(衣類なのでころもへん)
4 痩せるの「痩」
5 貪るの「貪」(貧困の貧は×)
6 語彙の「彙」
7 嗅ぐの「嗅」地獄の「獄」(犬→○大→×)
8 召喚の「喚」
9 応募の「募」
10 礎の「はね」の部分
11 喪主の「喪」
12 拐帯の「拐」
13 概念の「概」
14 擬声語の「擬」は、てへん
15 厳粛の「粛」(必ず書き順通りに練習すること)
16 桟敷の桟(意味を考えて、へんのミスをなくす)
17 衝突の「衝」と均衡の「衡」
18 専らの「専」と浅薄の「薄」の微妙な違い
19 駆逐と「逐」と未遂の「遂」の使い分け
20 戴冠の「戴」(載→×)※車ではなく、異
読みでも「たいかん」と書くように。
21 謎の点は、2てんしんにょう(点が2つ)
最後に
漢検2級は、数週間の勉強で受かるほど甘くありません。
そのくらいの期間で受かる人は、教科書を一周しただけで頭にほとんど入るような天才です。
いくら勉強しても次の日には忘れるのが人間の脳です。
こちらを参考にしてください。

最低でも1.2ヶ月は勉強するようにしましょう。
あなたの漢検2級の無事合格を祈っています。
(漢検準2級の攻略はこちら)

勉強におすすめのアイテム!
実際に使っているブックスタンドです。
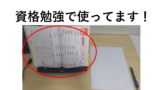


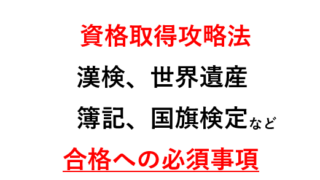
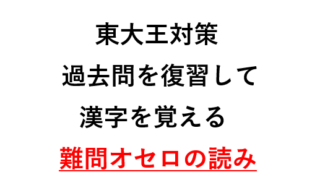


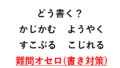
コメント