暗記を定着させるには、1ヶ月程度の時間が必要。
勉強をした後、10分程度の睡眠(仮眠)とってから、再び復習をすることで、記憶が効率的に定着できる。
以上2つのことを実証する記事です。
エビングハウスの忘却曲線について
受験勉強をした人なら一度は聞いたことがあるであろう、エビングハウスの忘却曲線。
エビングハウスの忘却曲線とは
ある事柄を覚えたとき、そのときの記憶の状態は100%であるが
①20分後には42%忘れる
②1時間後には56%忘れる
③9時間後には65%忘れる
④1日後には67%忘れる
⑤2日後には73%忘れる
⑥6日後には75%忘れる
⑦1ヶ月後には79%忘れる
というものです。
記憶の天才ではない限り、人は「一旦覚えた!」と思っても忘れていく生き物。
(エビングハウスの忘却曲線に基づいた勉強法とは)
一度忘れてしまったもの、中々思い出せないものを、定期的に復習して思い出すようにし、脳に必要な情報だと認識させ、できるだけ記憶の低下を防ごうとするもの。
短期記憶と長期記憶
物事を勉強して暗記をする際に重要になってくるのが、短期記憶と長期記憶です。
短期記憶
覚えたと思ったけど、すぐ忘れてしまうもの。
これが20分後には42%忘れていることに繋がります。
例)一夜漬けで勉強して「覚えた!」と思って、いざテストに臨んだら、半分以上記憶から吹っ飛んだ。
そんな経験、ないでしょうか。それが短期記憶です。
長期記憶
いつでも思い出せる状態。
また、思い出そうと思えば思い出せる状態。
脳に「この情報は大事だよ!」と何度もメッセージを送ってあげることで、長期記憶化がしやすくなります。
ちなみに「思い出せなくて、悔しかった事柄」なども、長期記憶化されやすくなります。
だから、暗記は繰り返し!とにかく反復!と言っています。
あの河野玄斗さんでさえ、そう言っている程。
そしてもう1つ、記憶の定着の仕組みについて面白いデータがあります。
「それが、睡眠」
人間は、記憶したものは睡眠をしているときに脳に定着させるという傾向があります。
(寝ているときに必要な情報と不必要な情報を整理しているため)
そのため、暗記を夜にして、情報が整理された朝に復習するのが効率がよいとされています。
なので
(何度も繰り返し勉強する)
→「これは必要な情報だ」と脳に認識させる
→寝ている間に「必要な情報の方に整理させる」
→記憶が定着化
という流れを狙います。
※以下の動画を参考にしています。
ブレイクスルー佐々木さんの動画
私は、エビングハウスの忘却曲線と睡眠と記憶の関係の両方を使い「長期記憶」に効率よく定着させる方法はないか考えました。
それが、10分勉強(暗記)して、その後、仮眠を10分をとるというものです。
それを1日3セット行います。
総使用時間は、たったの1時間です。
これだけで暗記ができるとしたら相当効率がいいと思います。
ということで、実際に実験してみました。
暗記のルール
①期間は1ヶ月
②初めて聞く首都を計20個覚える(わざと覚えにくい首都を厳選)
①イエメン(サナア)
②エリトリア(アスマラ)
③オマーン(マスカット)
④ガーナ(アンクラ)
⑤ガンビア(バンジュール)
⑥エストニア(タリン)
⑦ラトビア(リガ)
⑧リトアニア(ビリニュス)
⑨ルワンダ(キガリ)
⑩リビア(トリポリ)
⑪ナミビア(ウィントフック)
⑫ニジェール(ニアメ)
⑬パラグアイ(アスンシオン)
⑭ボリビア(ラパス)
⑮マリ(バマコ)
⑯モーリシャス(ポートルイス)
⑰レバノン(ベイルート)
⑱コスタリカ(サンホセ)
⑲シエラレオネ(フリータウン)
⑳セネガル(ダカール)
の計20個。
③実験方法
1)期間は1ヶ月。以下に示す方法を1日3セット行う。
最初の1週間は毎日、それ以降は1週間に1回。
2)初めて聞く首都を計20個覚える。
※国の名称から、首都を導く。
例:レバノンという名称からベイルートを思い出せたらOK
3)勉強時間は1セットにつき10分とし、覚え終わったら、10分間の睡眠をとる
(目をつぶるだけでOK、ただしこの10分は何も考えない。)
※(1)学校の休み時間が基本的に10分程度なので、10分とした。
※(2)睡眠を取る際は、クラシックなど、音声が入らない曲で、雑音が入らないようにする。
4)睡眠が終わったら、また10分間の暗記を行う
(勉強10分、睡眠10分の計20分を1日3セット行う)
5)暗記をする際、覚えた首都を消していって、覚えていない首都だけ残すという暗記法を適用しない
(覚えた覚えてないに関わらず、必ず20問を繰り返し解く)
6)勉強を始める前に必ずテストを行い、1日経った理解度を把握する
※以下の3つのグループに分けることで、詳細な理解度の把握を行う。
A:答えられた問題
B:思い出せそうになったが結局思い出せなかった問題
C:お手上げだった問題
7)暗記したとき以外の時間は、一切覚えた事柄に関しては触れず、思い出さないようにする
8)日時は必ず21:00~24:00までの間に行う
0~7日目
1週間勉強を行った結果、以下のようなグラフで表すことができました。縦軸は問題の正解数になります。

(0日目)
0日目はとりあえず全て暗記を行ったということで、定着度100%(20問)としました。
(1日目)
20問中覚えていたのは2問のみ。残りの18個は、思い出せる気配もありませんでした。
1日一生懸命暗記していても、翌日には90%も忘れていることが分かります。
ここが、暗記をする際に最初にぶち当たる壁です。
ちなみに復習し、何回か記憶していく中で、何とか記憶できそうなものは、いくつかありました。
(2日目)
20問中覚えていたのは4問。
昨日覚えていく中で「これとこれは覚えれそう」と思っていたものが、2問覚えられていました。
残りの16個に関しては、なんとなく思い出せそうなのはいくつかありました。
しかし、まだまだ長期記憶への定着には程遠いと感じました。
(3日目)
20問中覚えていたのは6問。
昨日覚えられていた4問は全て覚えており、新たに2つ覚えられた結果となりました。
答えをみて「なんとなくだけど思い出せそう」と感じたのが何問かありました。
ここからが伸び悩みの時期がくると予想してました。
(4日目)
20問中覚えていたのは9問。
昨日の6問は全て覚えており、新たに3つ覚えられた結果となりました。
(5日目)
20問中覚えていたのは12問。
昨日の9問は全て覚えており、新たに3つ覚えられた結果となりました。
5日目は、少々頭痛がしていた中でのテストでしたが、意外にも長期記憶化されていました。
5日経って「昨日覚えていたものが忘れていた」という問題が0問なのは意外すぎる結果でした。
(6日目)
20問中覚えていたのは13問。
昨日の12問は全て覚えており、新たに1つ覚えられた結果となりました。
未だに1度も正解できたものを忘れてしまったという問題はありません。
(7日目)
20問中覚えていたのは14問。
昨日の13問は全て覚えており、新たに1つ覚えられた結果となりました。
(結果と考察)
1週間、以上の記憶法を試した結果、70%程度の記憶ができ、1度覚えたものが翌日以降忘れてしまったということが一度もありませんでした。
7日目終了時点で、グループ毎に分けると
A:答えられた問題:14問
B:思い出せそうになったが結局思い出せなかった問題:2問
C:お手上げだった問題:4問
という結果になりました。
Cの4問に関しては、暗記をするには避けて通れない、自分にとって非常に長期記憶に移行しにくい単語です。
これらは、ただ単に反復記憶では厳しくなります。なので、工夫して記憶する必要があります。
これらの結果より、1日60分((10分暗記+睡眠休憩10分)×3セット)勉強法は、ある程度有効であると言えます。
実質30分で1週間勉強し続ければ、70%近く脳に定着させることが可能と考えれば、効率的に勉強することができるのではないでしょうか。
※今回は覚える対象を20個としましたが、覚える数が多ければ、それだけ定着率も下がると考えられます。
例えば「1度に40個」を対象にしたら、70%もいかないかもしれないということです。
今回は検証のため、一度確実に覚えたと思える首都も1週間繰り返し勉強するという、効率が悪い暗記法を用いました。
なので、覚えられてないもの、覚えられそうなもの、覚えたものの振り分けをして、配分をしながら学ぶ暗記法を併用すれば、もっと記憶の定着率が上がるのではないかと思います。
そして、これから1週間、覚えた事柄を寝かせて、全く復習しない状態でどれだけ忘れているかを検証しました。
(1週間学習から1週間後)
以下のようなグラフで表すことができました。

1週間で10%を70%まで記憶の維持を持って行くことに成功しましたが、1週間後には、50%まで下がっていました。
前回答えられなかった問題は全滅し、新たに覚えていたはずの問題が4問忘れていた結果になりました。
(1週間学習から2週間後)
今度は、下記の暗記法を行います。行う日は火曜日と木曜日の2日間。
日曜日が検証日です。
これまでは、記憶の定着を実験するため、単に反復記憶法を用いました。
今回は、覚えられてないもの、覚えられそうなもの、覚えたものの振り分けをして暗記を行う際に効率のいい方法を用いることにしました。
また、どうしても覚えられそうもないものに関しては、工夫をしながら、記憶を定着させるようにしていきます。
10分勉強(暗記)して、その後、仮眠を10分をとるという方法は変えていません。
覚えられていないもの、覚えられそうなものが20個中10個あったのでそちらを重点的に対策を行いました。
残りの10個については、ほとんど目を通していません。
結果、以下のようなグラフで表すことができました。

今回は、20個中15個と、75%まで達成という過去最高の結果となりました。
間違えた5個は、前回要対策に分けられた10個のうち5個。逆に言えば、5個は覚えられていました。
前回までとは違うところは、次回は思い出せそうな感触があったことです。ギブアップ状態の問題は0でした。
1週間後、全く同じ方法で、もう1度実験をしてみることにします。
(1週間学習から3週間後)
今週も、先週と全く同じ方法で暗記を行いました。
前回は15個を覚えられていたので、残りの5個を徹底対策しつつ、忘れそうなものも忘れずにフィードバックを行いました。
結果、以下のようなグラフで表すことができました。

ついに、全問正解を達成することができました!
実験をし始めて「1ヶ月間」です。
まとめ
今回の実験は、あえて覚えにくそうな首都を20個選出し、それを最低限度の勉強時間で如何に長期記憶化できるかという目的でした。
もちろん、勉強時間は多ければ多いほど、いいことには変わりありません。
人間が何かの事柄を覚えたとき、それを長期記憶化するには、約1ヶ月間続けて暗記を頑張れば、記憶が効率よく保たれるということが分かりました。
(大事なこと)
①勉強をした後に睡眠をとり、余計な情報を入れこまない
→勉強した後にスマホやTVなどをみるのはNG(余計な情報が入ってしまい、記憶の整理ができにくくなるため)
②テスト勉強等をする際には、なるべく1ヶ月前から暗記科目は対策するようにする
以上のことを意識して、なるべく効率的に記憶を維持できるよう頑張りましょう。


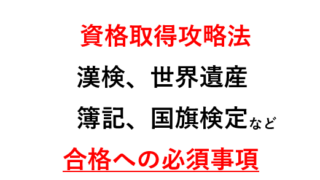
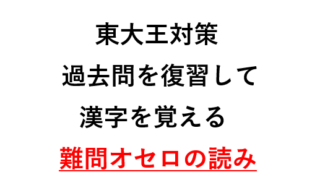
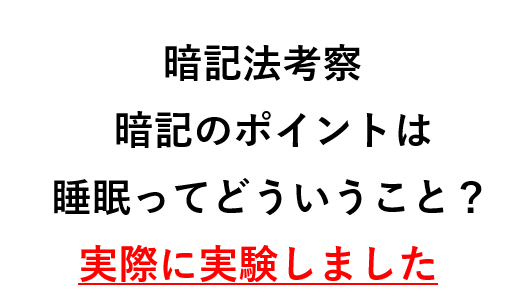


コメント